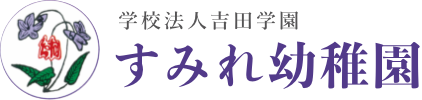2025.04.15
すみれだより
すみれだより 12月巻頭言
<登園・降園のときに思うこと>
園に行った日には、登園と降園のときに入り口でお迎え、お見送りをしております。すみれだより2月号では、「あ」のつく5つのことば、「安全」「安心」「明るい」「挨拶」「相手をおもう」について記しました。この中で、登園、降園に関わることばに「挨拶」があります。
挨拶を国語辞典で引くと、元は「禅家で師と修行僧が問答を交わす意」と書かれています。ほかの修行僧より一歩前に出て師匠と目を合わせながら問答を行っている様子が想像されます。おそらく始めに言葉を交わし問答に入ったため、それが現在の「挨拶」の意味として残ったのではないでしょうか。まさに、師匠とのコミュニケーションのはじめの言葉になるわけです。
武蔵野市の教育委員の在職中に、市内の小中学校の訪問を行う機会が数多くありました。訪問したときに子どもたちが挨拶をしてくれる学校では、気持ちよく校内を歩くことができました。幼稚園の近くにある武蔵野市立第一小学校では、幼稚園の前の大正通り等、周辺の道路を「あいさつロード」と名付け、挨拶に関係する子供たちの標語を掲示しています。本園の大正通り側にも標語が掲示されております。また、各学校の卒業式では教育委員会として定型の文書が用意されますが、それに加えて卒業生に「挨拶ができる人になってほしい」ということを祝辞としてお話ししました。このことは、入園説明会でも毎回話しているので覚えている方もおられるかと思います。そのためか、今年の入園の際の親子面接では、挨拶について触れられた方が複数おられました。
挨拶の良さは、「相手をおもう」ことにもつながります。私はムーバス(武蔵野市営のコミュニティバス)に乗るとき、降りるときに必ず挨拶をしています。もし自分がそうされたら、気持ちよく運転ができるのではないかと思うからです。新人の運転手さんでも2,3回もすると丁寧な挨拶をしていただけるようになります。顔見知りになると、大正通りで通過するバスをよけようと振り向いたときに、運転手さんから手を振って挨拶をしていただけるほどになりました。このように、挨拶は相手の気持ちを和らげるとともに、自分の気持ちも明るくすることができます。もし、挨拶をしても返してくれなかったら少し悲しい気持ちになるのではないでしょうか。
子どもたちは、園の活動の中ですべてのクラスで食事の時、皆で「いただきます」「ごちそうさま」という挨拶をしています。けれど、1人になった時、必ずしも自分から挨拶ができるようになっているわけではありません。
ご家庭においても保護者の皆さまが継続的に挨拶をするように心がけることによって、子どもも自然にできるようになっていくのだと思います。
私は、卒園生が小学校に入学したときに、「すみれ幼稚園から来た子どもたちはきちんと挨拶ができる素敵な人だ」と思っていただけると、とても嬉しく思います。 理事長 渡邉一衛